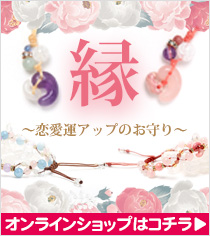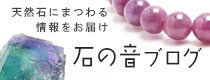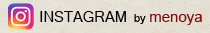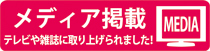パワーストーン・天然石のオリジナルアクセサリー
地球のかけら
【第61回】オブシディアン
2010年2月24日

※画像はウィキペディアより
私だけかもしれないんだけど、オブシディアンと黒耀石(こくようせき)って、その名前から受ける印象って、なんだかずいぶん違う気がしない?
いやいや、オブシディアンも黒耀石もまったく同じ石の英名と日本名なだけなんですよ。
でも、オブシディアンっていうと、ビーズになっていたり、ペンダントトップに使われていたり、手でにぎにぎできるように丸くカットされていたりする癒し系の石って感じ。

※画像はウィキペディアより
ところが、黒耀石っていうと旧石器時代の鏃(やじり)とかナイフに使われていた「道具」っていう印象。


※画像はウィキペディアより
「この鏃は黒耀石で作られています」とはいうけど、「オブシディアンで作られています」とはいわないからそんな印象になったのかな。
そのオブシディアン、主成分が二酸化珪素(にさんかけいそ)であることから「天然ガラス」って呼ばれている。ガラスっていうことは窓とかのガラスと同じもの。
二酸化珪素を人工的に溶かして固めた人工ガラスに対して「自然に溶けて固まった」ものが天然ガラス。
自然に溶けるっていったいどうやって溶けるのかというと、これはもう火山の爆発しかない。
珪素を多く含むマグマが空気に触れたり水に触れたりして急激(もう瞬時)に冷えると天然ガラスができる。
だから火山国の日本はとくに多い。日本だけで70か所以上の産地がある。
もちろん美しいものとなると場所は限られるけれど、北海道、長野県、島根県、大分県、長崎県あたりが有名。
それと要因は違うけど、隕石の衝突で珪素が溶かされてできたモルダバイトやリビアングラス、テクタイトもでき方としては同じ天然ガラス。
それから、オブシディアンの中には固まる際に部分的に脱ガラス作用とかいうものを起こして斑に白くなるものがある。それがスノーフレークオブシディアン。
また、レインボーオブシディアンは、インクルージョン(内包物)として針状の角閃石(かくせんせき:アンフィボール)が平行にたくさん入ることにより七色に発色する。
さて、ここで意外な事実を。
実はオブシディアンは鉱物ではないのです。
? と、思ったよね。
だって、どう見ても鉱物だもん。
でも、どの本を見ても鉱物ではないと書いてある。
鉱物は「結晶であること」が絶対的な定義なんだけど、オブシディアンは非晶質で結晶ではない。
石英や玉随(ぎょくずい:カルセドニー)、瑪瑙(めのう:アゲート)、それからロードクロサイトの縞々のヤツなんかは非晶質っぽく見えるんだけど、それらは非常に細かい結晶がギュギュッと固まったちゃんとした鉱物。
それに対しオブシディアンはその分子がすでにバラバラでまったく整列していない。整列していないということは結晶になっていないということ。
強いていうなら、石ではなく岩石に分類されるそうだ。
だから黒耀石も本当は黒耀岩が正しいらしい。
んー、岩石って鉱物が固まったものをいうんじゃなかったっけ? なんて思ったりするけど、ここから先は学者さんレベルじゃないとちゃんと答えられなさそうだ。
しかも、同じ非晶質のものとしてオパールがあるんだけど、オパールは「例外」として鉱物と呼んでいいんだってさ。
でも、このままわからないで終わらせるわけにはいかない。そこで、自分なりに調べてみた。
その結果、これまた意外な結論にたどり着いた。
それはこの、分子がバラバラになっている状態というのは、実はこれ液体なんです。
そう、オブシディアンは液体だったんです。
液体?! 液体って、どういうことよ!
って、当然思いますわな。
んー、たとえば、こう考えてみて。
「流れる水の時間を止め、それを切り取ったような」そんな感じ。
それはあくまでも水で、けして氷じゃない。
それがオブシディアン。
どうかな、ちょっと強引すぎるかな?
最後に。オブシディアンを持っている人、もし割っちゃったときは本当に気をつけてね。
古代のナイフとして使われていたように、その割れ口は刃物と同じ。

※画像はウィキペディアより
割れ口が貝殻状になることがオブシディアンの特徴のひとつだけど、その切れ味は切れなくなった包丁のそれ。
指を切ったら、いつまでも痛いぞー(経験者談)。