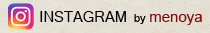パワーストーン・天然石のオリジナルアクセサリー
地球のかけら
【第3回】惚れたら負け!?宝石は''女性のもの''へ
2007年4月 1日前回、宝石の歴史をちょこっと考えてみた。
約3500年前、聖書に書かれたそのときから始まり、「魔力を持った石(マジカルジュエリー)」として、主に戦に勝つためのお守りとしてその歴史を刻んでいった。
その後、勝った者たちが自らの力を示すものとして剣などを宝石で飾るようになり、最終的に国が権威の象徴として宝石を所有するようになった。
と、ここまでが前回のあらすじである。
なるほど、確かに王様が被っている王冠なんていうのは象徴そのもの。外交の時や儀式の時にそれを被り、他の国の人たちを威嚇していたんだろうな。
中には30キロ(!)を超すものまで作られていたっていうんだから大笑い。当時のようすが目に浮かびます。どこかの国で大きな王冠を作ったって聞いた王様が「じゃあ、ウチはもっとデカイのを作る」ってなって、それを聞いたまた別の王様が「いや、ウチはもっとデカイのを」「いやいや、ウチなんて」ってなったに決まってる。
想像してみて。頭の上に30キロ。巨大なスイカでも10キロないんだよ。被った瞬間に首が骨折。王様になっても戦いは続くんだね。
まあ、そんなふうにガンバって宝石を身につけていた王様が過去には大勢いたわけだけど、現在、宝石を男のものと考えている人はいない。
いったい、いつの間に宝石は女性のものになったのだろう。今につながる宝飾品の元祖は誰なのか。
ちょっと調べてみると、それは意外と最近の話で、300年ほど前の18世紀初頭だったようだ。ところはフランス。
「あー、やっぱりフランスかあ」という感じだが、そのころのフランスは世界でもっとも裕福な国家のひとつで、イギリスと世界一を争っていた大国だった。そんなフランスに最高の宝石が集まるのは仕方がない。
当時の国王はルイ15世。

富を湯水のごとく使い愛人をたくさん囲っていた王様で、外国からのお客様に会うときは、いつもまばゆいばかりに光り輝いていたそうだ。世界史的には彼のせいで国の財政が悪化し、フランス革命につながったといわれているのだから豪快である。
その15世のお妃様の名前がマリー・レチンスカ。

ポーランドから亡命してきた元王様の娘。どうやら彼女が宝石を宝飾品として使った最初の女性らしい。
読んでみた本には、彼女が「王の装身具を解体し自分好みの宝飾品に作り替えた」と書いてある。
うーん。さらっと流しているけど、実はこれってすごいことをしているんじゃないのかな。
だって亡命してきたってことは、国を追い出されたってことで、そんな「元お姫様」と結婚してもフランスには何の得もない。結婚できただけでも奇跡的なことなのに、権威の象徴を王様から取りあげた上、自分のために作り替えているんだから。
「あら、あなた。ワタクシが欲しいといっているのですよ。何か文句でもおあり?」
「いや、それは代々……、あのその……、いえありません」
といっていたかどうかはわからないけれど、惚れたら負けってことなのかな。もしかしたら、このことで「宝石は女性が喜ぶ」と認識した15世が、愛人作りに大いに利用したため財政が傾いたのかもしれないけれど。
なにはともあれ彼女が宝石を権威の象徴から女性の宝飾品にしたのは間違いのないとこ
ろだろう。
その後、15世の孫にあたる16世の王妃マリー・アントワネットが、レチンスカの残した宝飾品をさらに自分好みの細く繊細なものに作り替えたという。現在の指輪やネックレスの始まりはこのときといえるかもしれない。
現代において、王様のいる国は世界に数えるほどしかない。フランスにももう王様はいない。
しかし、その数少ない王国のひとつにイギリスがある。イギリス王室は、まあ何かと話題が多いけれど、近々王様が交代しそうなんだよね。
それで、新しく王様が即位するときは、戴冠式(たいかんしき)という王様になるために王冠を被る儀式をおこなうんだけれど、当然、王冠と一緒に宝石もたっぷり登場するはずなんだ。
戴冠式は世界中でテレビ中継されると思うから、その時どんな宝石が登場するのか、今からとっても楽しみです(不謹慎)。
追伸
4月になりました。新入学生、新社会人のみなさん、希望に胸を膨らませ、ぜひ新しい生活を楽しんでくださいね。
私たちにとっては宝石採集シーズンの到来です!
さっそく活動開始。手始めに蛍石(フローライト)を探しに行って来ます。
結果は次回報告します。

参考文献
フェーマスダイヤモンド : イアン・バルフォア著 徳間書店
ジュエリーの歴史 : ジョージ・エバンス著 八坂書房
ヨーロッパの宝飾芸術 : 山口遼著 東京美術